すぱいすのページ
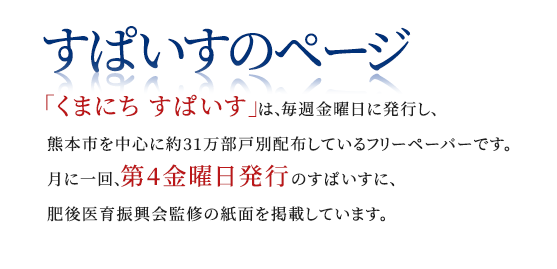
「あれんじ」 2013年8月3日号
【専門医が書く 元気!の処方箋】
医療の現場に生かされる 漢方薬・漢方診療
| 漢方薬や漢方医学は身近なようで、案外知らないことも多いものです。 そこで今回は、日本での漢方医学・医療の変遷や医師養成教育の変化、診療の中で漢方医学がどう生かされているかを紹介します。 |
| はじめに |
|
漢方薬や漢方医学を医療の現場に生かすことが必要だといわれています。多くの検査を行うことなく、患者さんの訴えをよく聞き、腹診、脈診を中心に診療を行う漢方の診察方法に期待が集まっているように感じられます。検査方法が豊富でなかったゆえに発達した診療法が求められているのかもしれません。 |
| 明治期に一度否定された漢方医学 〜日本での漢方診療の歴史 |
|
明治期に西洋医学、特にドイツ医学の導入が決定される以前は、漢方診療は日本の医療の中心でしたし、江戸期には日本独自の漢方医学が発達していました。 |
| 求められている漢方医学教育の実施 〜医学教育の変化 |
|
ここで、日本での医師養成の仕組みに簡単に触れておきます。 |
| 「冷え」と「ほてり」 〜漢方診療が得意とする症候 |
|
現在の日本で行われている漢方診療には、大きく分けて以下の3つの流れがあるように思われます。 |
| 現代医学の治療と併用 〜診療の現場から |
|
診療では、現代医学の治療と併用して漢方薬を使用するという医師が多いのではないかと思います。 |
| 最後に |
|
漢方診療では、薬をある特定の病名に対して処方することはなく、症状や病態に対して処方することが治療の中心です。 |
| 今回執筆いただいたのは |

熊本大学医学部附属病院
医療情報経営企画部 宇宿(うすく) 功市郎教授 1975年3月熊本県立熊本高等学校卒業 1981年3月鹿児島大学医学部卒業 内科、神経内科研修修練 1996年4月鹿児島大学助教授 (医学部医療情報管理学) 医療情報学、漢方医学の教育研究 2006年1月から現職 |